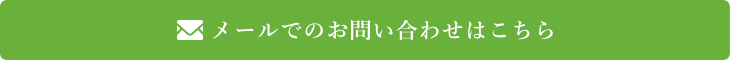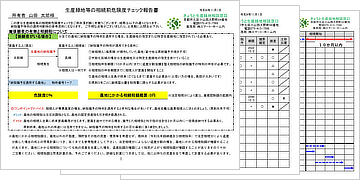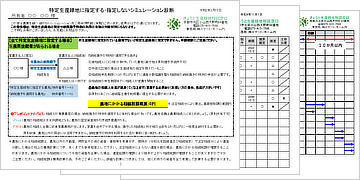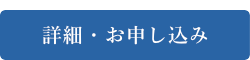- ホーム
- 生産緑地の相続対策Q&A
生産緑地の相続対策Q&A
父の所有する農地が生産緑地だと聞きましたが、どういう意味ですか?
お父様は都市部に500㎡以上の農地を所有されており、30年以上農業経営を続けることを条件に市町村から生産緑地の指定を受けておられます。
生産緑地の指定を受けたメリットとして、固定資産税・相続税などの税制上の優遇措置が受けられます。
デメリットは、有効活用が一切不可となり、宅地化して売却・賃貸・建築することができなくなります。
1992年に生産緑地の指定を受けているケースが多く、その場合には2022年で30年の営農義務が終わりますので、宅地転用できる可能性があります。
ただし、いつ生産緑地の指定を受けたのか?納税猶予の特例を利用しているか?によっては宅地転用できないケースもあります。
また、2022年以降も生産緑地の継続を希望する場合、特定生産緑地を選択すれば10年間、生産緑地と同様に固定資産税・相続税などの税制上の優遇措置が受けられます。
父が農地を相続した際に納税猶予を受けているそうですが、何のことか分かりません。
市町村から生産緑地の指定を受けている都市部の農地をお父様が相続された際に、終身(亡くなるまで)農業経営を続けることを条件に、その農地に係る相続税額の大部分について相続税の納税が猶予されています。
猶予であって免除されているわけではありませんので、お父様が亡くなられる前に農業経営を辞めてしまった場合、納税猶予が打ち切られますので、猶予された相続税額と猶予されていた期間の利子税を2か月以内に一括納税しなければならなくなります。
猶予を受けていた期間が長いと高額な利子税が加算されます。
そのため、納税猶予を受けている農地を宅地転用する場合や売却を検討される場合、必ず生産緑地の税務に詳しい税理士に前もって相談してください。
誰に相談したら良いか分からない場合には、私たちきょうと生産緑地相談窓口にご相談ください。
都市部に農地があり、相続税が心配。どれぐらい課税されるのか分からず不安です。
農地は面積が大きく、都市部の土地の相続税評価額が高額な為、農地を相続される方が農業経営を継がれない場合、相当な金額の相続税が課税されることが多いです。
相続税は、相続発生から10か月以内に納税する必要がありますので、事前の対策が大変重要です。
まずは、資産全体の把握等が必要となります。
農地が生産緑地の指定を受けているか?
農地とそれ以外の不動産の相続税評価は?
相続する人が農業を続けるか?
金融資産等はいくら位あるか?
生命保険の内容は?
法定相続人の人数は?
以上のような内容を把握しないと、相続税がどれくらいかかるのか計算できません。
また、節税する方法は無いか?
あるなら、どれを選択するか?
節税しきれない場合は、どうやって納税するか?
これらを合わせて検討する必要があります。
農地の税務や相続対策は複雑ですので、農地の相続税務や対策に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。
誰に相談したら良いか分からない場合には、私たちきょうと生産緑地相談窓口にご相談ください。
私は現在サラリーマンですが農業を継いで生産緑地を維持することができますか?
将来農業を維持したいので納税猶予を受けて農業経営を継ぐ予定です。リスクはないし農地も維持できるが、何も問題ありませんか?
確かに先祖代々の農地を維持することは大切ですね。
納税猶予を受けた場合、農業経営を継いだあなたが亡くなるまで終身農業を続けることを条件として農地にかかる相続税の大部分を猶予されます。
農地を維持するために良い制度ですが、そのリスクとして、もし、あなたが亡くなる前に農業経営を辞めた場合、納税猶予が打ち切られてしまいますので、猶予された相続税額と猶予されていた期間の利子税を合計した税額を2か月以内に一括納税しなければならなくなります。
また、高齢や病気等の理由で農業経営が困難になった場合でも、以下の基準を満たさない限り、納税猶予を継続しながら農地を貸付することができませんでした。あまりにも厳しすぎる基準で、簡単に利用できない制度でした。
2018年9月1日以降は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律により、生産緑地の賃借がしやすくなる法改正がありました。
また、あなたが納税猶予を受け、あなたのお子様が農業を継がない場合には、お子様の代に相続税支払いの問題を持ち越すことになります。
以上の理由から、安易に納税猶予を選択せず、良く検討されることをお勧め致します。
生産緑地の危険度チェックサ ービスのサービスをお申し込み頂きますと、納税猶予を選択するべきか?等についてもアドバイスさせていただきます。
高齢や病気になった場合に農地の貸付が認められる基準
- 精神障害者手帳(障害等級1級)の交付を受けている
- 身体障碍者手帳(障害等級1級又は2級)の交付を受けている
- 介護保険の要介護認定(要介護5)を受けていること
生産緑地があり、将来農業を継ぐ予定だが慢性的な赤字。農業を継いで収入も安定させたい。どうしたら良いか分かりません。
農業経営には経費がたくさんかかる為、慢性的に赤字の方からご相談を受けることが多いですね。
安心して農業を継ぐためには、生産効率の悪い農地や農地以外に所有されておられる未利用地等を有効活用して、安定した不動産収入を得られるようにすることを検討しましょう。
まずは、生産緑地の現状把握が必要となります。
耕作しやすい農地はどれか?
耕作しにくい農地はどれか?
有効活用しやすい農地や未利用地はどれか?
その上で、生産緑地を解除できる可能性の有無を調べ、いつから有効活用できるのか?を知りましょう。
未利用地があれば即、有効活用が可能ですが、賃貸経営に向いている立地かどうか?賃貸需要や先行きはどうか?
検討する必要があります。
農地の有効活用の判断は、都心部の土地の有効活用よりも難易度が高いため、複数の分野の専門家が必要となります。
難易度の高い生産緑地の問題に対処するために、私たちきょうと生産緑地相談窓口は活動しております。
節税と収益率の向上を両立する資産運用のコンサルティングを得意としておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
父が高齢で農業経営を私に移譲したいが、その場合でも納税猶予は受けられますか?
納税猶予は、お父様が亡くなられる時まで農業経営を継続していたことが前提ですが、以下の要件のいずれかに該当すれば、お父様の死亡時にあなたが相続税の納税猶予の適用を受けられます。
農業経営を移譲しても納税猶予が受けられる要件
- お父様とあなたが住居と生計を一にしていて、かつ、一緒に農業に従事している場合
- お父様が特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受ける為、あなたに農業経営を移譲する場合
納税猶予を途中で打ち切ると相続税プラス利息がさかのぼり課税されて大変らしいですが、良く分かりません。どういうことですか?
納税猶予が打ち切られた場合、猶予された相続税額と猶予されていた期間の利子税を2か月以内に一括納税しなければならなくなります。
農地は面積が大きく、都市部の土地の相続税評価額が高額な為、多額の相続税が課税されることが多いです。
更に高額な相続税に対する利子税も合わせて納税しなければなりませんので、計画的に納税猶予を打ち切る場合でも慎重に検討されることをお勧め致します。
納税猶予を打ち切った場合の一例
平成5年1月にお父様が納税猶予を受けられていて、猶予された相続税額が1億円であり、平成26年12月末に納税猶予を打ち切った場合
平成27年2月末までに以下の税額を納税しなければなりません。
猶予された相続税額1億円+利子税9400万円 = 合計 1億9400万円
23年間で約2倍の税額になってしまいます。
どの農地で農業を続け、どの農地を有効活用するか判断できない。誰に相談したら良いですか?
生産緑地等の農地の相続問題と有効活用の両方に精通した専門家に相談するようにしてください。
しかし、実際には、そのような専門家はほどんどいません。
その理由は、農地の有効活用の判断は、都心部の土地の有効活用よりも難易度が高いため、複数の分野の専門家を必要とするからです。
きちんとした相談先でなかった場合、後で後悔することになるかも知れません。
農業を続けた場合と続けずに有効活用した場合では、固定資産税や相続税の金額が大きく異なります。
また、有効活用する場合には、賃貸市場の現状と将来性を良く調べる必要があります。
安易に節税だけを重視したり、賃貸市場調査せず有効活用すると後々大変な状況になっているケースが多いです。
難易度の高い生産緑地の問題に対処するために、私たちきょうと生産緑地相談窓口は活動しております。
お気軽にご相談くださいませ。
父は専業農家、私は会社員のため全部の農地を継げない。農地の一部は有効活用の為宅地化し、一部だけ生産緑地を維持して納税猶予を受けられますか?
こういったご相談は良くお受けしますね。
原則的に一部だけ生産緑地を維持して農地の一部を有効活用することは可能です。
但し、一部の市町村の農業委員会によっては生産緑地の一部解除が認められない場合がありますので、事前に良く調査する必要があります。
まずは、生産緑地の危険度チェックサービスをお申し込み下さい。
生産緑地の一部解除に関するアドバイスも行っております。
農業だけでは生計が成り立たないので、相続後の生産緑地を一部解除して賃貸マンションを建てたいが相続税が心配。いくらぐらい相続税がかかるか知りたい。
生産緑地の一部解除可否に関する調査と、ご希望されている計画に対してかかる相続税の試算はどちらも非常に大切です。
特に生産緑地を解除した場合には多額の相続税が課税される場合が多いので、良く検討されることをお勧め致します。
また、不動産の税務に詳しい税理士に相談するべきです。
その上で、有効活用のプランについて市場調査や将来予測がきちんとされているか確認する必要があります。
プロに任せておいたら安心と思っておられる方が多いですが、賃貸経営は自己責任ですので、ご自身でも勉強されるようにしてください。
誰に相談したら良いか分からない場合は、こちらをご覧ください。
農地を全て相続したいが、相続税が払えそうにない。どうしたら良いですか?
何も対策をしない場合には多額の相続税がかかってしまう場合が非常に多いですね。
相続前からできる対策と相続後にできる対策がありますが、有効な対策には時間が必要な場合が多いため、相続前から対策されることをお勧めしております。
相続が発生してからでも対策は取れますが、選択肢は少ないです。
相続税を節税する方法はいくつかあります。
代表的なものは納税猶予の特例を利用することです。
しかし、相続した人が亡くなるまで農業を続けることが必要であり、慎重に検討する必要があります。
相続前であれば農地の一部を有効活用して賃貸物件を建築すれば節税効果があります。
この場合、有効活用する立地の賃貸市場調査と将来予測がとても大切です。
相続前、相続後、いずれのケースも、複雑な農地相続の実務に詳しい専門家に相談する必要があります。
誰に相談して良いか分からない場合はこちらをご覧ください。
農地に適さない土地だけ生産緑地を解除して売却できますか?
可能です。
ただし、いつでも生産緑地を解除できるわけではありません。
多くの生産緑地は1992年に指定されており、30年の営農義務があります。
指定から30年後の2022年に営農義務が満了した場合、生産緑地を解除して売却することが可能になります。
ただし、納税猶予の特例の特例を受けている生産緑地には30年ではなく、更に厳しい終身(亡くなるまで)営農義務が課されていますので注意が必要です。
2022年の到来または、相続の発生や営農を継続できない事故の発生等のタイミングで、生産緑地を継続するかどうか選択できるようになります。
その場合の選択肢は以下の通りです。
- 全ての生産緑地の指定を継続し、本人または相続人が営農を継続する
- 農地に適さない部分は、生産緑地を解除(買取申し出)して売却し、それ以外の農地は生産緑地の指定を継続し、本人または相続人が営農を継続する
- 全ての生産緑地を解除し、営農を辞める
行政により対応が異なりますが、生産緑地法の改正で300㎡以上あれば生産緑地の指定を受けられる自治体もあります。
上記2のケースでは、300㎡もしくは500㎡以上の生産緑地を確保すれば、それ以外の生産緑地の指定を解除して売却することも可能です。
上記3のケースは、生産緑地を解除すると固定資産税の優遇が無くなり、5年間かけて段階的に増税され宅地並み課税されます。
放っておくと税負担が厳しいので、有効活用するか?売却するか?売却の上、売却資金で別の収益不動産を購入するか?
等を検討する必要があります。
また、生産緑地を解除した場合、相続時に納税猶予の特例が利用できませんので、相続税の資金をどうやって確保するか?検討しておく必要があります。
生産緑地を継続するかどうか?
継続するならどの部分が良いのか?
次の世代は農業を継続する予定があるのか?
将来の相続税負担はどれ位か?
生産緑地の問題は多岐にわたり複雑ですので、生産緑地問題の実務に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。
誰に相談したら良いか分からない場合は、私たちきょうと生産緑地相談窓口にご相談ください。
父はできれば私に農業を継いで欲しいと思っているが、会社員で転勤もあり、継ぐかどうか迷っている。
こういったご相談は多いですね。
確かに農業を継いでも、転勤があって農業が続けられなくなることも考えられます。
転勤が決まっても、以前までは生産緑地を貸すことは認められていませんでした。
2018年6月に都市農地の貸借の円滑化に関する法律が制定され、要件を満たす場合は、生産緑地を個人または株式会社や農業生産法人等の法人に貸し出すことができるようになりました。
この法律ができるまでは、生産緑地を貸すと納税猶予が打ち切りになり、すぐに相続税と利子税の合計額を納税しなければいけませんでしたが、この法律の要件を満たして賃貸する場合は納税猶予も継続できます。
農業を継ぎたいが転勤があって心配。という方には上記の制度が利用できます。
注意点は、借りたいという相手方がいることが必須条件です。
営農しやすい農地でない場合、借り手が見つからないケースも考えられます。
道路付けや形状等が農業に適しているか?を確認の上、検討されることをお勧めします。
生産緑地の問題は多岐にわたり複雑ですので、生産緑地問題の実務に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。
誰に相談したら良いか分からない場合は、私たちきょうと生産緑地相談窓口にご相談ください。
具体的にご相談をご希望の場合、以下のサービスがご利用いただけます。
生産緑地の危険度チェックサービスをお申し込み頂きますと、農業を継いだらどうなるのか、継がない場合どうなるのか、その結果が分かります。
これからどんな対策をすれば良いのか?等もご提案させていただきます。
父が高齢で生産緑地の維持が大変。今すぐ売却や有効活用できないか?
今すぐ売却や有効活用ができたら、お父様も楽にできるうえに収入もアップして全て上手く行きそうですが、実は、生産緑地の指定を解除することは難しい場合が多いです。
但し、一定の状況に限り生産緑地の指定を解除できる場合があります。
解除の可能性について生産緑地・都市農地お調べサービスで調査致します。
まずは、生産緑地の危険度チェックサービスをお申し込み下さい。
生産緑地の解除に関するアドバイスも行っております。
父の生産緑地を売って欲しいと言われたが、生産緑地がどういうものかも知らず、どうしたら良いか分からない。
生産緑地を売却したいというご相談も良くお受けしますね。
まず、生産緑地についてですが、お父様は都市部に500㎡以上の農地を所有されており、30年以上農業経営を続けることを条件に市町村から生産緑地の指定を受けておられます。
生産緑地の指定を受けたメリットとして、固定資産税・相続税などの税制上の優遇措置が受けられます。
デメリットは、有効活用が一切不可となり、宅地化して売却・賃貸・建築することができなくなります。
つまり、生産緑地は基本的に売却することができないのです。
但し、一定の状況に限り生産緑地の指定を解除できる場合があります。
解除の可能性について生産緑地・都市農地お調べサービスで調査致します。
まずは、生産緑地の危険度チェックサービスをお申し込み下さい。
生産緑地の解除に関するアドバイスも行っております。
農業を継ぐ予定はないが、かなり相続税がかかりそう。どうやって支払ったら良いのか?なるべく相続税を減らしたいがどうしたらいいの?
農地は面積が大きく、都市部の土地の相続税評価額が高額な為、農地を相続される方が農業経営を継がれない場合、相当な金額の相続税が課税されることが多いです。
相続税は、相続発生から10か月以内に納税する必要がありますので、事前の対策が大変重要です。
相続税を節税する方法はいくつかあります。
代表的なものは納税猶予の特例を利用することですが、相続人が農業を続けない場合には利用ができません。
相続前であれば農地の一部を有効活用して賃貸物件を建築すれば節税効果があります。
この場合、有効活用する立地の賃貸市場調査と将来予測がとても大切です。
また、土地の境界を確定し、相続発生後に土地の区割りを変える(分筆する)ことで節税できる場合もあります。
金融資産が多い場合には生前贈与も有効です。
いずれにしても、節税対策は時間が必要なものが多いので、早めに対策に取り掛かることをお勧めします。
また、節税対策をしても相続税が課税される場合は、納税資金をどうやって確保するのか検討しておく必要があります。
納税するための資金づくりには、農地または未利用地を一部売却する。生命保険を活用するなどの方法があります。
相続対策や納税対策は、複数分野の専門家の知識と経験が必要です。
相続前、相続後、いずれの対策のケースも、複雑な農地相続の実務に詳しい専門家に相談する必要があります。
誰に相談して良いか分からない場合はこちらをご覧ください。
|
生産緑地の
京都・大阪・奈良の生産緑地をお持ちの方は、まず危険度をチェック!相続対策への第一歩を踏み出してください。 |
特定生産緑地に指定する・
多くの生産緑地についてアドバイスしてきた、コンサルタント集団が、「特定生産緑地に指定する・指定しない」をシミュレーション診断いたします。 |