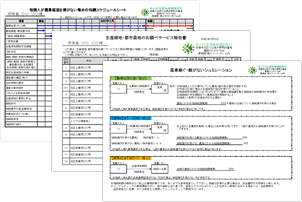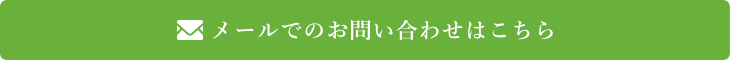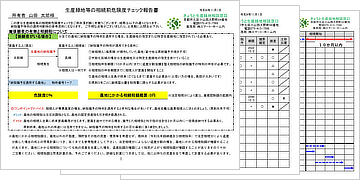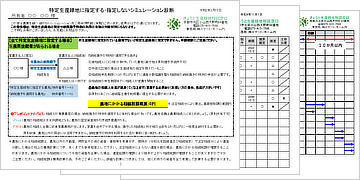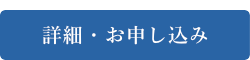- ホーム
- 農地コンサルタントが見た、生産緑地の相続対策ブログ
- そもそも農地とは
そもそも農地とは
2017/07/12農地の定義について

「農地とは何ですか?」と聞かれたら、あなたはどう答えますか?
見た目が田んぼや畑なら農地だと答える方がほとんどではないかと思います。
しかし、それは正確な答えではありません。
では、農地とは一体何なのでしょうか。
今回は、農地の定義について見て行きましょう。
農地の定義
- 耕作の目的に供される土地であること
- 現に耕作されている土地、又は、いつでも耕作できる土地であること
- 耕作とは土地に労費を加え肥培管理(ひばいかんり:作物を栽培するとき、施肥・水やり・中耕・土寄せ・害虫の駆除などを総合的に管理すること)を行って作物を栽培すること
- 農業委員会の農地台帳に登録されていること
以上が農地法に定められている農地の定義となります。
法律が関係すると専門用語があるために何のことか分かったようで、実は良く分かりませんね。
簡単に言いますと、「農地」とは、土地の現況が、きちんと耕作を行って作物を栽培している土地、又は、いつでも耕作できる状態の休耕地等であり、かつ、農業委員会の農地台帳に登録されている土地のことです。
ここでのポイントは、現況が耕作地であるかと、農業委員会の農地台帳に登録されているかどうかです。
良くある質問で、登記の地目が「田」や「畑」だから農地ですか?というものがあります。
登記の地目だけでは農地とは判断できませんので、まずは農地台帳を確認してみましょう。登記が田や畑でも現況が宅地等の場合はそもそも農地ではありませんので現況も併せて確認してみましょう。とお答えしています。
他にも、農業経営者(農家)ではないのですが、面積の広い雑種地を所有していて固定資産税が高いので、畑にすることで固定資産税を安くできませんか?という質問もあります。
結論から言いますと、それはできません。という回答になります。
登記自体は現況主義の為、現況が畑になると雑種地から畑に地目変更登記できる可能性があります。
ただし、地目が畑になっても、農業委員会の農地台帳に登録されていないと、固定資産税の農地評価を受けることができません。
農地台帳に登録される為には、農家の資格がないといけませんが、新規に農家資格を得る為には、農業委員会に「認定申請書」や「営農計画書」、「資金計画」などを提出し、許可を得なければなりません。
更に、農地を3,000平方メートル(3反)以上所有するか借りないといけません。
固定資産税を安くするためだけに新規で農家になる方はおられないと思いますので、現実的ではありませんね。
食料自給率を維持する為に、国策で農地の税制を優遇していますので、農地の定義に当てはまらない田や畑等の場合には固定資産税は安くならないのです。
|
生産緑地の
京都・大阪・奈良の生産緑地をお持ちの方は、まず危険度をチェック!相続対策への第一歩を踏み出してください。 |
特定生産緑地に指定する・
多くの生産緑地についてアドバイスしてきた、コンサルタント集団が、「特定生産緑地に指定する・指定しない」をシミュレーション診断いたします。 |